駅弁と聞いて、まず思い浮かぶのはどんなお弁当だろう? 多くの日本人の記憶に刻まれているのは、あの素焼きの釜に入った「峠の釜めし」ではないだろうか 🍱 群馬県の横川駅で1957年に誕生したこの駅弁は、累計販売数1億8000万個を突破し、今なお進化を続けている。製造元の荻野屋は2025年10月15日に創業140周年を迎えるが、ただ伝統を守るだけでなく、『鬼滅の刃』『エヴァンゲリオン』『シティハンター』『推しの子』といった人気アニメとのコラボレーションで若年層への扉を開いている。なぜこの駅弁は時代を超えて愛され続けるのか? その秘密に迫る。
素焼きの釜に込められた革新的アイデア
「温かい駅弁が食べたい」─そんな乗客の声から生まれたのが、峠の釜めしの特徴である素焼きの釜だ。
四代目社長の高見澤みねじさんが考案したこの容器は、益子焼の陶器製で保温性に優れている。直径140mm、高さ85mm、重量725gの釜は、栃木県益子町の窯元つかもとで製造されており、上半分の茶色い部分には「横川駅」「おぎのや」の文字が刻まれている 🏺
1950年代後半、駅弁といえば冷たい幕の内弁当が当たり前だった時代。陶器の容器を使うという発想は、当時としては画期的だった。実用新案登録も取得したこの釜は、ご飯を温かいまま提供できるだけでなく、食べ終わった後も器として再利用できる。帰宅後も旅の思い出として手元に残る、そんな「お土産感」も計算されていたのだ ✨
口コミを見ると、40代の利用者からは「東京の自宅に持ち帰って食べても、ご飯がほんのり温かくて感動した。陶器の保温性に感服」という声が。50代の方は「益子焼の釜の手触りは昔と同じ。この釜でちょうど一合のご飯が炊ける」と懐かしさを語っている。
秘伝の9品目が織りなす味の調和
峠の釜めしの中身は、シンプルだが計算し尽くされている。秘伝の出汁で炊き上げた自家精米のコシヒカリの上に、色彩豊かな9種類の具材が載る。
その9品目とは、鶏肉、椎茸、筍、牛蒡、杏子、栗、うずらの卵、グリーンピース、紅生姜。醤油ベースの薄味の炊き込みご飯に、それぞれの具材が個性を発揮する。30代の愛好者は「あんずの甘酸っぱさが絶品。具材の好きな順に並べると、1位あんず、2位しいたけ、3位鶏肉」と語る 🌰
創業当初からのレシピを基本的に変えていないというのも驚きだ。徹底した衛生管理のもと、国産・外国産を問わず厳選された素材を使用。まるで家庭で愛情を込めて作るお弁当のような工程で、一つひとつ丁寧に製造されている。
別添えのプラスチック容器には、小なす、小梅、わさび漬けも入っており、これが口直しにちょうどいいアクセントになる 💚
140年の歴史が語る、ピンチをチャンスに変える力
荻野屋の歴史は、1885年(明治18年)、信越本線横川駅の開業とともに始まった。創業者・高見澤仙吉が駅構内でお弁当や菓子を販売したのが原点だ。
当初は竹の皮に包んだおむすびを販売していたが、売上は低調。そんな中、1957年に四代目社長となった高見澤みねじさんが、常識を覆す「峠の釜めし」を考案した。発売開始当初は1日30個程度の売上だったが、『文藝春秋』に紹介されたことをきっかけに人気が爆発 📈
1962年には、モータリゼーション時代の到来を見据えて国道18号沿いに「峠の釜めしドライブイン横川店」を開業。鉄道への依存を減らし、販売戦略の幅を広げた。1987年時点では1日平均1万個、多い時は2万5千個を売り上げる人気商品に成長した。
しかし1997年、信越本線横川〜軽井沢間の廃止という大きな打撃を受ける。それでも「ピンチをチャンスに」を合言葉に、新幹線車内での販売開始など新たな販売チャネルを開拓。2012年からは環境に配慮したパルプモールド容器版も販売し、時代のニーズに対応し続けている 🌱
若年層へアプローチ、アニメコラボの戦略
実は荻野屋の調査によると、10代の約半数(48.5%)が「駅弁を買ったことがない」と回答している(2023年調査)。また駅弁業者数は1960年代の最盛期には全国で400を数えたが、現在は77にまで減少。駅弁市場の縮小は明らかだ。
荻野屋首都圏事業部の浦野恵造部長は語る。「駅弁の認知度は年齢が高くなるほど高いが、若年層は弱点。そこでアニメとのコラボを実施している」
エヴァンゲリオン(2021年) では、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』とタイアップ。初号機カラー(紫・緑)の益子焼の陶器を使用した特別版を1,500円で販売した。さらに興行収入95億円突破を記念して、蓋裏に碇シンジのイラストが焼き付けられたサプライズエディション(1,900円)も限定販売。群馬県や長野県、東京の店舗で数量限定で展開され、朝8時の整理券配布には長蛇の列ができた 🎬
シティハンター(2024年) では、『劇場版シティーハンター 天使の涙』とコラボ。「獠と香、絆の100tハンマー釜めし」として販売され、購入場所によって掛け紙のデザインが異なる仕様に。購入特典として掛け紙がプレゼントされ、ファンのコレクション欲を刺激した 🔫
推しの子(2025年9月) では、「日本全国project【47都道府県の子】」で群馬県代表のMEMちょを起用。「MEMちょ釜めし」「星の輝き釜めし」の2種類を各2,600円で販売(9月16日〜10月6日)。描き下ろしイラストの掛け紙と釜敷(全2種)が特典として付き、群馬県の横川店・高崎売店、長野県の諏訪店、オンラインショップで展開された ⭐
20代の利用者からは「推しの子コラボで初めて峠の釜めしを知った。MEMちょの描き下ろしイラストが可愛くて、釜めしも美味しくて大満足」という声も。アニメコラボは確実に新規顧客層を開拓している。
駅弁を取り巻く環境変化への対応
電車のスピードアップにより、移動中に駅弁を食べる機会は確かに減少している。しかし浦野部長は語る。「売れる場所や食べられるシーンが変わってきている。デパートの駅弁フェアではものすごく賑わうし、売れる」
実際、東京エリアには複数の直営店を出店。GINZA SIXや銀座博品館などに「ORBcafe」を展開し、惣菜や地酒も扱う新業態を開始。2023年からは一部店舗で「峠の釜めし 冷蔵タイプ」の販売もスタートし、多様化するニーズに対応している 🏙️
空の釜容器は回収後、破損がないか確認し、使用できるものは洗浄・殺菌してリサイクル。公式サイトでは釜を使ったご飯の炊き方やレシピも公開し、持ち帰った容器の活用方法を提案している。
60代の方からは「会議で駅弁を出したら、陶器の器が旅情を感じさせて場が和やかになった。重たい陶器のお弁当を配達してくれるのはありがたい」という声も。ビジネスシーンでも活躍する峠の釜めしの姿がある 💼
変わらぬ味、変わり続ける戦略
峠の釜めしの本質は変わらない。素焼きの釜、秘伝の出汁、9品目の具材。しかし荻野屋は決して過去の栄光に甘んじることなく、時代に合わせて進化し続けている。
アニメコラボ、環境配慮型容器、東京進出、冷蔵タイプ開発─伝統と革新の両輪で走り続ける姿勢こそが、70年近く愛され続ける理由なのかもしれない。
横川駅前の本店で食べるもよし、新幹線の車内で味わうもよし、デパートの駅弁フェアで手に取るもよし。どこで食べても、あの素焼きの釜を開ける瞬間のワクワク感は変わらない。次はどんな新しい挑戦が待っているのか。峠の釜めしの進化から、目が離せない 🚄✨
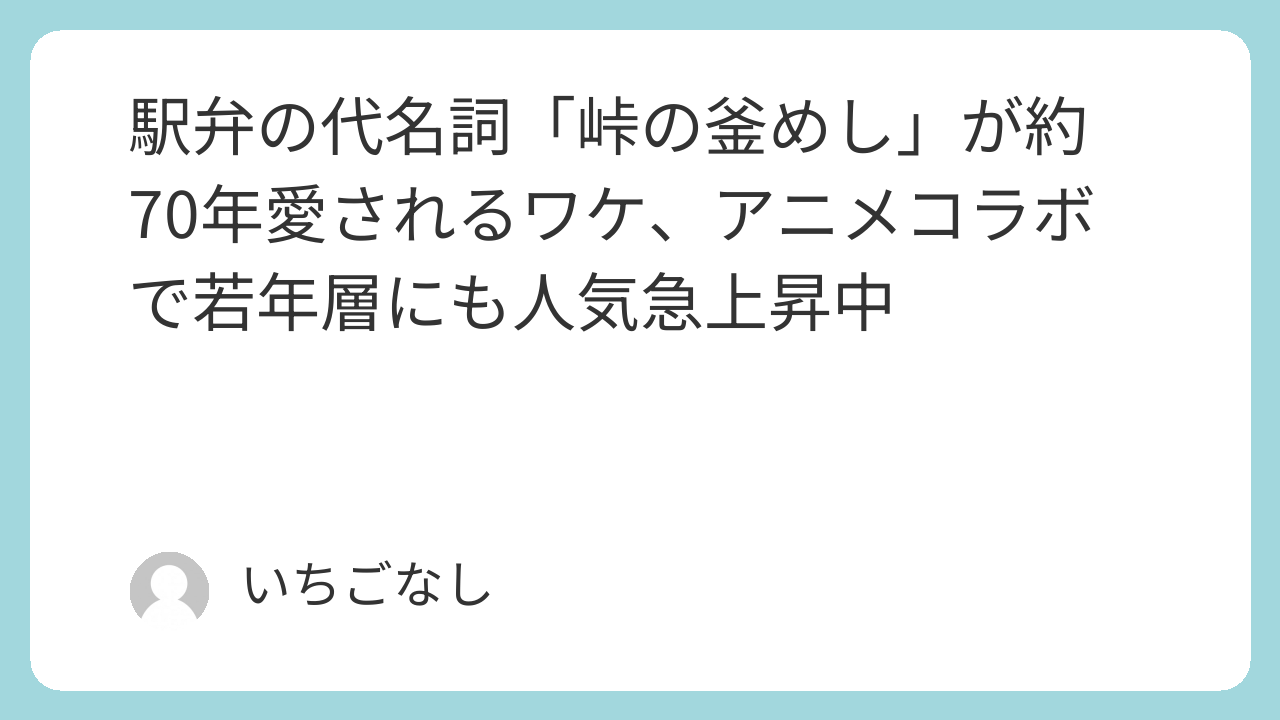
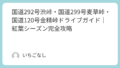
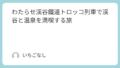
コメント